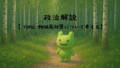現在の農林水産省は、小泉進次郎大臣のもとでコメ政策の見直しを進めています。
備蓄米の活用や、農業の集約化、技術の導入などの生産性の向上を図る施策に取り組んでいますが、消費者と生産者の両方が納得を得ることに苦戦している状態です。とても難しい問題だと思います。この記事では、コメ政策について説明します。考える機会の一つにしていただければと思います。
日本の農業の現状
【食料自給率について】
・米は、100%近く自給。
・野菜は、7割以上自給。
・小麦・大豆・飼料穀物は、ほとんど輸入に依存。
総合的に食料自給率38%で問題視されているが、日本の食料自給率が低い理由は、肉や乳製品、果物、穀物の消費が多いからで、米は国内生産がほぼ100%に近いので、米と野菜の国内生産だけで食事を構成すれば、カロリー自給率は大幅に上がる。食料自給率が低いというイメージが大きいが、コメの問題と絡めてくることは違和感がある。
【収益性】
個人農家は、兼業農家が7割以上。農業だけで生活できないケースが多い。
2022年の農林水産省の調査によると、農業所得の平均は約120万円/農家である。
小規模農家と大規模農家の比率は、1ha未満が約59%、1~10haが41%、10ha以上は0.3%。農家の数は小規模が多いが、生産量と売上は、経営体の12%が、全体の販売額の78%を占めていて、その大部分が少数の大規模農家である。
【高齢化】
平均年齢は68.4歳。後継者がいない農地が放置され耕作放棄地が全国で増加。
ただ、大規模農家は若年層の参入が進んでいて、小規模農家は高齢化が進行し、後継者不足が深刻である。大規模農家と小規模農家では、平均年齢に大きな違いがある。
日本の農業の歩み
1942年 食糧管理制度(米を政府が買い上げ、販売し、農家の収入を安定化させる制度)制定。生産者は政府に売却することを義務づけられ、政府が消費者に配給することで、公平な食糧配分をした。
1945年 農家は米を強制的に安く供出させられる一方、闇市(非合法な市場(ブラックマーケット) のことで、政府の配給制を通さずに物資が売買された市場のこと)では高値で取引される時期があった。
1960年 政府は、農家の不満を和らげ、農業の生産力を維持するため、米を高く買い取る逆ざや政策を実施。この赤字は税金で補填。農家から高値で米を買い上げ、消費者へは安く販売する仕組み。
農業基本法(農業所得を他産業と均衡させることを目的とした法律)制定。米を高く買い取る政策を続け、米を優遇する。結果的に、米は他の作物に比べて過剰に保護され、優遇された農産物となった。
1970年 食生活の変化、つまり、パンや肉の消費が増えたことにより、米の消費が減少した。財政負担の増大で、制度が持続困難になった。過剰生産で米が余ってしまったので、減反政策(政府が農家ごとに作付面積の上限を決定)。
1995年に食糧管理法廃止、2018年に減反政策廃止し、米の作付面積は農家の自由になりました。この変化は農家の自由度を高めましたが、小規模、高齢農家にとっては厳しい状況になりました。しかし、個人農家は、平均年収120万円と、貧困や高齢化の問題で苦しんでいる一方、法人化した農家、輸出向けの高付加価値作物に取り組む農家は、年収1,000万円以上のケースも増えています。生産量の総量は、工夫している農家のおかげで、ある程度維持されているので、コメの供給量には大きな問題は出ません。
問題は小規模農家が潰れること。このことに対して、時代の自然な流れと受け入れることも一つの考え方だと思います。実際、農業の効率化や規模拡大が進むのは世界的な傾向です。若者が都市に移動して地方が高齢化することや、非効率な農家が減ることは自然なことです。しかも、人口減少している現状だと、集約化が合理的な選択です。しかし、大事なポイントは、小規模農家が持っていた機能は完全に代替されないという点です。小規模農家が減って集中生産が増えると、災害や病害虫の被害が致命的になる可能性がうまれます。地域の農家が潰れることで、地域社会の縮小を進めてしまったら、地域の伝統を喪失することになります。後継者がいなければ、伝統は消滅します。農業の祭りや伝統的な特産品も失っていきます。一度喪失すると戻らないので、文化を守る視点でも慎重に考えていかなければならないと思います。
国がある程度ルールを作ることは、国民にとって有益なこともあります。個人では、どうしても対処できないリスクをカバーすることができます。しかし、食糧管理法が廃止された時のように、ずっと優遇されていて、いざ放置されて、いきなり困ってしまった場合、国は責任を取るべきなのでしょうか。人間は本来、困難に向き合って自分の努力で生活を築くことが前提です。支援と自助のバランスは、国も国民も歩み寄りがないと、解決は難しいものだと思います。デメリットだけ取り上げて、敵対していても解決は難しくて、国は全体の幸せを真剣に考えて、国民は自力で解決に取り組むことが大切です。国が利権に縛られたり人気取りで短期的な解決に走ったりすることや、国民が制度に依存し過ぎて不満ばかりになることは、好ましい状態ではないです。また、国民が断片的な情報だけで、全体のイメージとして捉えてしまうことも良くないし、国やメディアが情報を偏りなく出し切らないことにも問題があります。国民も国やメディアも、それぞれ責任を持って情報を扱うことが大切だと思います。これは、コメ政策のことに関わらず、日本社会全体の在り方として、言えることだと思います。みなさまは、どう考えますか?